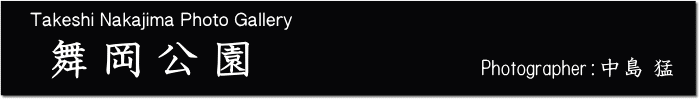|
東日本大震災で多くのボランティアが駆けつけたが、マスコミでの話題は少なかった。
ウキペディアの記事: 阪神・淡路大震災ブログで、「ボランティアの連中」は「観光気分で来た自分探し」「ただの野次馬観光客で、何の役にも立ちません。」「人から感謝されることを楽しみにやってきただけ」「被災していない人間に被災者の気持ちが分かるわけがない」「ボランティアは、被災者が食うべきものを食い、被災者が飲むべき水を飲み、被災者が寝るべきところで寝る」等と攻撃し、「プロに任せろ、被災地に必要なのは、プロだけです。」とボランティア不要論が展開された。
ボランティア活動の要素は一般に自発性、無償性、利他性、先駆性の4つである。一方、個人の自己実現の場として機能する自己実現性を持つことも知られている。自己成長の可能性が高められるなど、人生を充実する活動の一つでもある。厚生労働省の全国調査では、最大の人材源となっているのは主婦層および高齢者層である。キリスト教の影響が大きくボランティアの歴史が長いアメリカでは、高校生、大学生の時に一定のボランティアに従事するとキャリア形成につながるというシステムがあり認定資格制度が確立している。
自主性、無報酬を前提とするのがボランティア活動の定義だという意見もあるが、日本人が昨今忘れてしまった利他性=愛他性を育む上で、学生時代におけるボランティア活動は、キリスト教や仏教などの宗教の枠を超えてグローバルな人間性を育てる上で必要視する意見も多い。
さて現在のわが身を振り返ると、写真が最大の趣味なのに、街のいろいろなボランティア活動の影響を受けている。自治会長やシルバークラブの会長もボランティアである。現在の自治会長はなり手がなく数ヶ月説得された女性の方である。小生も話が出てから3ケ月経過してシルバークラブの会長をやらされるハメになった。今の自分は幸福か?やることが後から後から容赦なく、やってくる。活動をしている瞬間は結構熱中している自分を発見することもある。午前1時までパソコンに張り付いていることもある。何でやらなくてはいけないのかしぶしぶ準備している場合も多くある。健康を害してしまうのではと思うことも多々ある。近くの学校で4年間、舞岡公園の写真を展示し続けているが、これは明らかに自分の達成感の為であるといえるが。
曽我綾子が最近のテレビ番組で、確か、幸福とは「人に尽くす」ことを中心に論じていて、キリスト教精神も取り上げていた。小生も少々キリスト教をかじっている。
ウイキペディア情報のように、ボランティアをやるには、何らかの魂胆がある。それは「自分の為」か「他人のため」なのか、その混ざり合いか、その中間か?
|