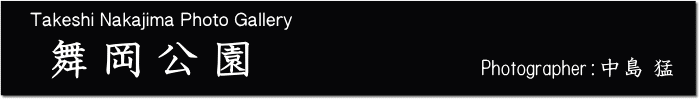|
いまさらながら、デジカメ写真の理想的な最終形態はなんであろうかと気になっている。
「当然プリントだ」という意見が大勢だろう。小生も、中級以上のモニターやプリンターを揃え、Photoshopを使い高品質プリントの作成に努めている。近隣自然大公園の風景や町の諸行事の写真プリントを自治会館や学校などで展示している。デジタル画像技術が躍進した現在でも、現実的に可能な大衆向け永続的展示手段はプリント以外にない。プリントが作品の最終形態と言える理由の一つであろう。
しかし、町の集まりで、自治会館にある比較的大型のテレビで写真を披露することもやっている(液晶プロジェクターは不鮮明だから問題がある)。又、自分のホームページでは10年近く月々写真を追加掲載している。 作品として見てもらえているのかなという先入観的疑問があるものの、結構受けていると思われる。
今やインターネットには写真作品が無数にあり、SNSでの気軽な展示、有名無名人のホームページやブログ、サイバーギャラリー、サイバーフォトコン、ネット写真販売・・・など盛んである。これらを、大衆はスマホ、タブレット、テレビなどを含めた千差万別の性能の電子画像装置(モニターと呼ぼう)で、これまた千差万別の環境光のもとで観ている。モニター画像は絶え間ない電流により作動するエレクトロニックスにより表現されており、厳密には絶えず変動し揺らいでいる、何かふわふわした、刹那的な展示なのだろうとも思えるが、作品鑑賞方法の一つとして、世界中に普及していると認めざるを得ない。
人間の鑑賞眼は、その性格、知識、経験、知的能力・・・などにより千差万別であるが、画像のディーテイルや観る時の環境光などの違いを脳で補正して鑑賞する(又はしてしまう)融通性と弾力性がある。そして、その筋のプロが厳選した作品は、展示方法に関係なく、大衆も名作として観て認める。話しは飛ぶが、世界的名作の絵画が世界的ギャラリーで展示されているが、原画劣化防止などのため、照明は総じて暗めでないかと思う。原作者はどういう光りと明るさで鑑賞してほしかったのであろうか。写真プリントの鑑賞でもほぼ同様であろうし、この点ではモニター画像もプリントも作品形態としては大差ないとも思える。
そうだ見逃せないポイントがある。人間(動物も)はすべての被写体を通常は反射光を目が捉えて脳で処理して観ている。人間にとっては、モニターで透過光画像を見るより、反射光で観るプリントの方が、自然で人間本能の郷愁に近いことになる。
モニターで観ている画像をプリントするには、作者の感性をフル稼働して、Photoshopなどのソフトを駆使し、プリンターや用紙とのマッチングに気を使い、厳密な画像補正をして仕上げる。その時の感性、環境光、プリンターや紙とのマチングなどの組合せは二度とない可能性がある。このプロセスを経たプリントは、ほぼ「世界でただ一つ」になりそうである。そして高度に進化した顔料系プリントの保存性はその価値を更に高める。
|